どうも!カワヤスです。
この記事ではスループットの最大化を妨げているものを考察してみました。スループットの本質を紐解き、改善への一歩を踏み出すきっかけになればと考えています。
なお、本記事で紹介する内容はエリヤフ・ゴールドラットさん著書の「クリティカルチェーン」に基づいています。この記事で紹介しきれないノウハウがぎっしり詰まっていますので、興味を持たれた方は、ぜひ本書を手に取ってみてください。
工場の経営改善、スループット改善、プロジェクト管理のヒントとなれば幸いです。この記事は、スループットを改善したい人、経営改善をしたい人、いつもプロジェクトがうまくいかない人やプロジェクトを任されたばかりでこれから進めていくという人にぜひ読んでほしい記事です。
結論
それでは早速結論です。
コストワールドとは何?経営哲学はスループットと何が関係あるの?となりますので、本記事では、マネジメントする人の視点に立ってこれらの概念を解説し、結論へ導こうと思います。
さてそれでは、コストワールドの世界へ行きましょう!
マネジメント
多くの企業では管理職、いわゆるマネージャーが存在します。
これらマネージャーはどのように評価されているのでしょうか。
もちろん、マネージャーなのですから、与えられた業務を部下に託しながら上手くマネジメントすることで評価されていると思います。
それでは、上手くマネジメントするとは、一体どういう意味でしょうか。
いろいろマネージャーを評価する指標はあるかと思いますが、絶対に欠かすことのできない2つの条件があると思います。
一方で、スループットも守らなければならない。
つまり、必要な製品を必要なクライアントに対価を払ってもらえるような形で届けなければいけません。たとえば、コストを上手く抑えた、経費を20%低く削減できたと言ったとします。しかしクライアントの半分を怒らせてしまいました。彼を優秀なマネジャーと呼んでいいのでしょうか?逆にスループットを守った、全てを納期内に出荷したと言ったとします。でも、そのために人をもっと雇って残響も限りなく増やしたとします。彼はいいマネジャーなのでしょうか?
コスト管理とスループット維持、この2つは絶対的に必要な条件です。どちらが欠けてもだめです。しかし、どちらも違うマネジメントモードを必要とするものなのです。
喩え
わかりやすくするために、喩えを用います。会社にはいろんな部門があります。研究部門、生産部門、経理、資材、配送…。それぞれをひと繋がりの鎖とみなします。

この鎖のどこがコストに相当するでしょうか。コストとは何でしょうか?コストは全ての部門で発生します。コストの発生しない部署などありません。会社全体のコストを把握するためには、各部門で発生したコストを合計すれば求めることができます。この鎖でコストに喩えることができるとすれば、それは重さです。どの輪にも重さがあります。全体の重さを知るには各々の重さを合計すればいいのです。
それで、何がわかるでしょうか?コストをコントロールするということは一つのマネジメント手法を意味します。皆さんはこの鎖全体の社長です。私はあなたの部下で、一部門、すなわちある鎖の輪のどれかひとつを任されているとします。社長であるあなたは私にも改善を要求します。従順である私はさっそく作業に入り、100グラムの減量に成功しました。しかしいったいこれがどういう意味なのでしょうか?
つまり、一つひとつの部門における改善は自動的に組織全体の改善に繋がるということを意味します。要するに、組織全体の改善を達成するには、多くの部門において部分改善を進めなければいけないということです。これをコストワールドと呼びます。
当たり前の話だと思っているでしょうか?でもどうして当たり前なのでしょうか?これが唯一の経営哲学だからでしょうか?いえ、そうではありません。当たり前と思うのは、私たちがこの経営哲学に染まっているからです。長年染まってきた経営哲学。おそらく産業革命が始まった頃からでしょう。
ここでスループットワールドに話を移しますが、このスループットワールドとコストワールドは相容れない哲学なのです。
スループットの本質とは?
鎖のそれぞれの輪は、資材調達、製造開始、製造終了、組み立て、出荷など、役割がある。それのどれかひとつの輪で作業が遅れたとします。会社全体のスループットはどうなるでしょう?スループットを考えるとき、重要なのは一つひとつの輪だけでなく、輪同士の繋がりです。これが重要になってきます。では、この鎖でスループットに相当するものはなんでしょうか?もし鎖を一つひとつの輪にしてバラバラにしても総量は変わりません。しかし、一つひとつの輪を繋いで鎖にしたとき、いったい何が決まるのでしょうか?
それは強度です。鎖の強さです。
たった一つでも輪が切れれば鎖は切れてしまいます。鎖の強度はゼロです。では、何によって鎖の強度は決まるでしょうか?強度の一番弱い輪です。
では、鎖の中で強度の一番弱い輪はいくつあるか?ひとつです。皆さんはまだ鎖の社長です。私もまだあなたの部下で、ひとつの輪を担当しています。強度の一番弱い輪はひとつしかありません。私の担当している輪は一番弱い輪ではありません。ここで、社長のあなたは私に輪を改善しなさいと再度命じます。私は頑張って輪の強度を高めました。以前の強さの3倍の強さにしました。皆さんは実はわたしの輪には興味がなく、興味があるのは鎖全体の強度です。
全体の強度はどれだけ増したでしょうか?ゼロです。どういうことか、わかりますか?
部分的にいくら改善したとしても、組織全体の改善には繋がらないのです。目指すのは組織全体の改善、強度アップです。組織全体の改善を図るためには部分的な改善をいくら行ってもダメだと言うことです。
まとめ
いかがでしょうか。ことコストだけを考えた場合、コストワールドの部分改善は組織全体のコストを下げることに働きます。一方でスループットを増やそうとしたときに、部分改善をいくらしたところで組織全体の改善にはつながらないのです。
私たちがスループットを改善するために必要なのは、鎖の中の一番弱い輪を見つけ、強化することです。逆にいうと、スループットの改善を妨げているのは、部分改善だということです。すなわち、コストワールドの考え方がスループットの向上を妨げていると言えます。
次回
スループットワールドとコストワールドは相いれない哲学だと述べました。次回はなぜ相いれないのか証明いたします。
最後になりましたが、本記事が皆様に少しでもお役に立てれば光栄です。今後ともカワヤスブログをお願いいたします。
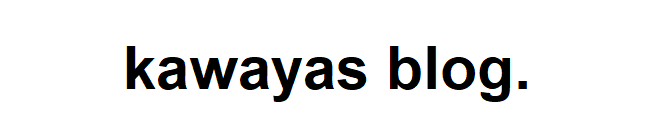


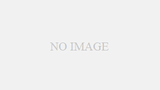
コメント